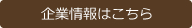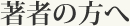無料版・バックナンバー
- ビジネス選書&サマリーのバックナンバーをご覧いただけます。

2007/06/08
キミがこの本を買ったワケ
-

用もないのに、日課のようにコンビニに立ち寄る人がいる。そして、
今日発売の雑誌や新商品をチェックしている。しかし、それほど頻
繁に新商品に出会うことはなく、結局いつもの商品を買って帰る。
あるマーケティング会社によると、消費者の85%は買うものを決めず、
単に新しいものを求めて店に行くという。それは、人が基本、新し
いもの好きだからだ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■■
■■ ビジネス選書&サマリー
■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<読者数53,484部>━
■今週の選書
■キミがこの本を買ったワケ
■指南役/フォレスト出版
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★本書の詳細、お買い求めは、→ http://tinyurl.com/33lnhp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
■■選書サマリー
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
世界初、人が物を買う理由を赤裸々に解き明かした本
【1】
用もないのに、日課のようにコンビニに立ち寄る人がいる。そして、
今日発売の雑誌や新商品をチェックしている。しかし、それほど頻
繁に新商品に出会うことはなく、結局いつもの商品を買って帰る。
あるマーケティング会社によると、消費者の85%は買うものを決めず、
単に新しいものを求めて店に行くという。それは、人が基本、新し
いもの好きだからだ。
私たちが新製品を求めるのは本能だ。アフリカの南端に生まれた私
たちの先祖は、そこに安住することはせず、新天地を目指して北へ
北へと北上を繰り返した。
だからこそ、人類は繁栄したのだ。我々が絶えず新商品や新天地を
追い求めるのは、DNAに刷り込まれた本能のせいなのだ。
【2】
人は、買い物という行為自体がたまらなく好きだ。商品を手に入れ
ることは嬉しいが、それ以前に買い物という行為が楽しいのだ。だ
からこそ機会があれば、常に買い物をしていたいのだ。
しかし、理由もなく買い物できるわけではない。買うキッカケが欲
しい。よくあるのが「がんばった自分へのごほうび」だ。「ごほう
び」というのは、買い物欲を満たす口実に過ぎないのだ。
もうひとつの正当な言い訳が「ブーム」だ。ブームなら、自分に対
して正当な言い訳ができる。ヨン様やハンカチ王子を応援している
主婦の何人が、本当に心の底から彼らを応援しているのか。
ブームに乗じていれば、買い物ができる。単に買い物が楽しいから、
その口実として彼らを応援している女性も、実は少なくないのだ。
【3】
寿司屋のカウンターでタコを注文したとき、本当は醤油が好きなの
に、つい「塩で」と言うことがある。このように、人には本心とは
別に惹かれるフレーズがある。
なんとなく口にしたくなる、そして周囲もそれを聞くと一目置きた
くなるフレーズだ。他にも「黒」「××っぽくない××」「手作り
感覚」「逆に言うと」「今年の風邪はお腹に来る」などがある。
しかし、それらのフレーズを口にする時、心がこもらない。ただ、
口先だけで言っている。だから、これらのフレーズを連発すると、
途端に薄っぺらに聞こえてしまうので注意が必要だ。
【4】
一般に、人は「選ぶ」のが苦手だ。選択肢が多すぎると、結局何も
買えないのだ。デパ地下に行って、どれも買いたくて仕方ないのに、
結局、何も買えずに帰ったことはないだろうか?
同じことは情報にも言える。90年代初め、どんな小劇場のマイナー
な公演情報をも網羅した「ぴあ」と、ビジュアル重視で、情報量が
極めて少ない「東京ウォーカー」が覇権を争ったことがある。
結果「東京ウォーカー」が勝った。理由は「ぴあ」は情報量が多す
ぎたのだ。「東京ウォーカー」は面倒くさくなかった。後日「ぴあ」
は情報量を減らすことで、部数を回復した。
【5】
同じ理由で「デパートよりも、セレクトショップのほうが好き」と
いう人も多い。これも、お店がある程度選んでくれていて楽だから
だ。マネキンのコーディネートが、そのまま欲しいのも楽だからだ。
他にも、例えば本屋の手書きPOPに「この本が人生を変えてくれ
た」など書いてあると、つい買いたくなる。そうでもなければ、新
刊本の洪水の中で、途方に暮れるはずだ。
ランキングも選ぶ手間を省いてくれる。オリコン、ベストセラー、
視聴率など、とにかく人はランキングが好きだ。そして、トップ5
に入っている作品なら、選んで安心と考えるのだ。
基本的に、我々は選ぶのが苦手なので、選択肢が多すぎると結局、
何も買えない。セレクトショップや手書きPOPは、そうした人の
習性にうまく応えている。
人は、こうした人間本来の習性に従って、無意識のうちに物を買っ
ているのだ。
★本書の詳細、お買い求めは、→ http://tinyurl.com/33lnhp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
■■選書コメント
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本書は、草場滋氏率いるエンタテイメントの企画集団「指南役」が、
「物を買う」メカニズムを明らかにしようとした本です。
百円均一の店で、本屋で、バーゲンの会場で、後から「なぜ、こん
なもの買ったんだろう?」と思った経験は、誰にでもあるはずです。
私は、しょっちゅう思っています。
お答えは、おそらく一つではありません。いろいろな要素が合わさ
っていますし、人によっても違うはずです。
その、いわば「神の手」の領域とも言うべきテーマに、真正面から
踏み込んだのが本書です。理詰めでなく、それでもきちんと、しか
も優しく答えてくれます。
なお、本書に出てくる日常は、美容院や回転寿司、百円均一などの
実例を筆頭に、松田聖子、スカイラインの「ケンメリ」、たまごっ
ちなど、私の世代には古くて懐かしい例がたくさん登場します。
本書を読んでもマーケティングの基礎知識が身に付くわけではあり
ません。教科書のように、体系立てて、網羅的に解説している本で
はないからです。
それでも、人に物を買っていただく上で大切な様々な要素を、きち
んと説明してくれます。シュガーマンやオグルビィなど、広告界の
巨匠たちの理論やフレーズも紹介しつつ、丁寧に解説してくれます。
そして、日常の出来事に「なぜなだろう?」と関心を持ち「もしか
したら、こうじゃないか?」と仮説を立てる癖がつくはずです。気
がつけばマーケティングのセンスが磨かれているはずです。
「せっかく読むのなら、ただ面白いだけでなく、ビジネスに役立つ
本がいい。ただ、仕事で疲れているので、堅苦しいのは嫌だ」そう
考えるビネスパーソンにお読みいただきたいと思います。
★本書の詳細、お買い求めは、→ http://tinyurl.com/33lnhp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
■■耽読日記 Vol.10
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ビジネス書をこよなく愛する藤井が、徒然に書いてます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●読書人脈は「宝の脈」と心得よ
この連載も10回を越えました。「いつまで続くかな?」「誰か、読
んでいるのかな?」と思いつつ、自己満足で書いています。
バックナンバーを整理してくれているウチの社員も「これ、要らな
いですよね?」と、バサバサ削除してました・・・
※
今思えば、結果的に読書が自分の人脈を作りのきっかけになってい
たことを感じます。今の私のおつきあいは、読書なしでは築き上げ
られなかったはずです。
私は、最初は単なる本好きでした。せっせと本を読んでいました。
しかし、いくら読んでも、時が経つに連れてどんどん忘れてしまう
ことが不満でした。
仮に憶えていても、それを実践したり引用したりする時に再確認し
ようとしても、膨大な蔵書の中から、どこに書いてあったか見つけ
出すことは至難の業でした。
そうした、読んで学んだことを、後で活用できるように、書籍のデ
ータ、そのエッセンス、自分の感想をまとめたメモを作り始めました。
最初は自分のために作っていたのですが、次第に他の人にもプレゼ
ントするようになりました。
当時、私は駆け出しコンサルタントでしたが、書籍の中にお客様の
役に立ちそうな内容を見つけては、その本をお薦めしたり、プレゼ
ントしたりしていました。
メモを書くようになってからは、それをメモに盛り込んで、プレゼ
ントするようにしました。これは、私の師匠が新聞の切り抜きをプ
レゼントしていたの真似たものです。
次第にお客様の引き止め策、またこれからお客様になっていただき
たい、いわゆる「見込客」の囲い込み策にも活用するようになりま
した。
その後、メルマガが流行し始め、自分も発行したと思ったとき、こ
の内容を送ることに思い至りました。
メルマガ「ビジネス選書&サマリー」は、こうして誕生したのでし
た。
(つづく?)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎このマガジンは、著者と出版社から掲載許可をいただいて配信し
ています。無断転載はご遠慮ください。(C) Copyright 1999-2007
──────────────────────────────
◎バックナンバー→ https://www.bbook.jp/backnumber
◎ご意見、お問い合わせは、→ info@kfujii.com
◎マガジン登録、変更、解除→ https://www.bbook.jp
──────────────────────────────
発行元:藤井事務所 責任者:藤井孝一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━