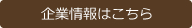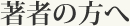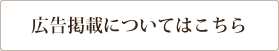無料版・バックナンバー
- ビジネス選書&サマリーのバックナンバーをご覧いただけます。

2008/01/28
ビジネスマンのための「発見力」養成講座
-

見えない物を見つける技術
新幹線に乗るとき、改札機には乗車券と特急券の2枚を入れる。出
てくるときは、どちらの切符が上になっているかご存知だろうか。
JR東海では、以前必ず乗車券が上になっていた。新幹線に乗る人
が、改札に入って最初に知りたい情報は、乗る電車が何で何番線か
ら出るのかということと、席は何号車の何番かということだ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■■
■■ ビジネス選書&サマリー
■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<読者数55,891部>━
■今週の選書
■ビジネスマンのための「発見力」養成講座
■小宮 一慶 /ディスカヴァー・トゥエンティワン
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★本書の詳細、お買い求めは、→ http://tinyurl.com/2agv5j
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
■■選書サマリー
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
見えない物を見つける技術
【1】
新幹線に乗るとき、改札機には乗車券と特急券の2枚を入れる。出
てくるときは、どちらの切符が上になっているかご存知だろうか。
JR東海では、以前必ず乗車券が上になっていた。新幹線に乗る人
が、改札に入って最初に知りたい情報は、乗る電車が何で何番線か
ら出るのかということと、席は何号車の何番かということだ。
だから、これらが書かれている特急券が上になっていたほうが、あ
りがたい。なぜ、こんな些細なことに気付くかといえば、ある「判
断基準」を持っているせいだ。
私の判断基準とは「お客さま本位か?」ということだ。経営コンサ
ルタントという職業柄、つねに「それはお客さま本位か?」という
視点から物事を見る癖がついているのだ。
このことから、私は「JR東海のサービスに対する考え方の一端が
見えた」と感じた。
【2】
些細なことでも気が付く私でも、JR東海がいつのまにか切符の出
し方を変えたことには気付かなかった。今では入れた順番と逆に切
符が出てくるようになっている。
特急券を上にすると乗車券が上に、乗車券を上にすると特急券が上
になって出てくるのだ。いつからこうなったか気付かなかった。わ
たし自身が「思い込み」のために、事実を見ていなかったのだ。
ここで二つのことがわかる。ひとつは「気にしていれば、ものは見
える」ということだ。どちらの切符が上になって出てくるのか、最
初に気付いたのはこれだ。
もうひとつが「思い込みがあると、ものが見えなくなる」というこ
とだ。JR東海の改札機の変化に気付かなかったのは、こうした理
由によるものだ。
【3】
ところで、私はよくお金を拾う。一度などは、三万円がひらひらと
落ちてきた。もちろん拾って、前を歩いていた落とし主の女性に渡
した。実際、お金は結構落ちているものだ。
だが、大抵の人は一万円札が落ちているはずなどないと思っている。
しかし、これは間違いだ。「お金なんてそうそう落ちているもので
はない」と思い込んでいるから、目に入らないだけなのだ。
私たちは、カメラのように目の前のものすべてを写すようにものを
見ているのではない。関心のあるもの、自分にとって必要なものだ
けを見るようにできている。
さて、ここで、あなたが今はめている腕時計を、実物を見ないで紙
に描いてみてほしい。縁取り、文字盤、時計の針、バンドの様子を、
少し時間をかけて真剣に思い出すのだ。
描いたら、実物と見比べてみてほしい。さて、出来映えはどうだろ
うか?毎日、何回も見ているはずなのに、意外と不正確ではないだ
ろうか?
【4】
ここでもうひとつ問題を出したい。腕時計を見ないで答えてほしい。
今、何時何分だっただろうか?時計のデザインにとらわれて、時刻
を気にしてはいなかったのではないだろうか。
このように、私たちは見るものと見ないものを、あらかじめスクリ
ーニングして見ているのだ。もともと見ようとしたものしか見えな
いとしたら、見ようと思わない限り見えないということになる。
つまり、自分には、もう十分見えているつもりになっている人には、
それ以上は、何も見えないことになってしまう。
どんなジャンルであれ、プロフェッショナルというものは、素人に
は見えないようなものまで見えている。これは、見れば見るほど、
見たいものや見ようと思うものが増えてくるからだ。
言い換えれば、物事には奥行きがあり、深いところまで見れば見る
ほど、その先にまだ見えないことがたくさんあることがわかってく
るのだ。
だから、ものを見る力を磨くには、まず自分には見えていないもの
がある、わかっていないことがある、という意識をもつことが、第
一なのだ。
★このマガジンをアップ・グレード?!
ココ→ http://www.kfujii.com/tcy06.htm
★本書の詳細、お買い求めは、→ http://tinyurl.com/2agv5j
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
■■選書コメント
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
セブンイレブンのロゴは、最後のnが小文字になっています。新幹線
の自動改札機は、乗車券と特急券が入れたのとは逆に出てきます。
同じものを見ているのに、人によって見えるものが全く違います。
そんな、日常のちょっとしたことに気づき、そこから、法則や本質
までを見出すことができる人がいます。そのコツを、物を見るプロ
フェッショナルである著者が、惜しみなく披露してくれます。
インターネットが普及して、入手できる情報の量が膨大になりまし
た。それでも、そこに何を見出すのかは、人によって異なります。
結果、そこから得るものも大きく異なってきます。
みんな同じ情報を見ているのに、そこから世の中の本当の動きを知
り、チャンスをつかむ人がいます。そういう人が成功します。成功
者の真似ばかりする人は、いわゆるカモで、いつも損をします。
見えない物を見るために必要なのは、ちょっとしたコツや心構えで
す。カモにならないためにも、ぜひ物を見る目を鍛えることをお薦
めします。
本書の特徴は、なんと言っても分かりやすさです。一般に、この手
の発想力を鍛える類の本は、外資系の戦略コンサルタントが、少し
斜に構えて書いているのが普通です。
そのため、事例が欧米の例だったり、大企業のものだったりと、我々
の日常には、馴染みのないものが多いのです。それが、不必要に理
解を難しくています
その点、本書の事例は、極めて日常的です。たとえば「サラダバー
のプチトマトのへたを取ってあれば一流ホテル」など、イメージし
やすくて、しかもすぐに使えそうなものばかりです。
だから、スラスラと面白く読め、どんどん頭に入ってきます。日ご
ろ熱心に情報収集しているが、どうも上っ面ばかりだと感じている
方なら、きっと楽しめるはずです。ぜひお読みください。
★本書の詳細、お買い求めは、→ http://tinyurl.com/2agv5j
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
■■耽読日記 Vol.41
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ビジネス書をこよなく愛する藤井が、徒然に書きます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●読書の目的は、活用
読書の目的は、活用することです。そのためには、単に字面を追う
だけでなく、三色ボールペンで書き込む作業、付箋で印を付ける作
業が、欠かせません。
つまり、読書とは、目玉と脳みそだけでなく、手も動かすことが、
とても重要なのです。手を動かすことで、理解と記憶を高めること
ができます。つまり、手の動きが脳の動きをより活発にするのです。
こうすることで、受け身になりがちな読書という活動を、能動的な
活動にすることができます。これが、読書を、より身のある活動に
する秘訣です。
こうして読み終わった本は、ボロボロになっています。(写真)自
分の知恵とアイデアの結晶が染みこんだ、他に代え難い自分だけの
財産です。
だから、私は本を人から借りて読むことをしません。図書館などで
借りて読むこともありません。立ち読みもしません。しませんとい
うより、できません。
なぜなら、読んでいるうちに、無意識に書き込んだり、折り曲げた
りしてしまう恐れがあるからです。何より、手を動かさずに読んで
も、読んだ気がしません。
また、自分が読み込んだ本を、人に貸すこともありません。自分が
書きこんだことを人に見られるのは、恥ずかしいからです。
何より、人に貸す可能性を意識しながら読むと、メモ書きの際も、
いろいろと憚られたり、気取ってしまうからです。
もちろん、仕事柄、読んで良かった本は人に勧めます。また、人か
らお薦めの一冊を尋ねられ、持っているなら貸して欲しいと頼まれ
ることもあります。
その時、「自分は、本を貸さない主義です!」というと人間関係に
角が立ちます。このような対応は、人たらし的ではありません。
そこで、私は自分が読み込んだ本を貸して欲しいと言われたときは、
書店で同じ本を買ってきて、あげるようにしています。
(つづく?)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎このマガジンは、著者と出版社から掲載許可をいただいて配信し
ています関係で、無断転載はできません。ご了承ください。
──────────────────────────────
◎バックナンバー→ https://www.bbook.jp/backnumber
◎ご意見、お問い合わせ、→ info@kfujii.com
◎マガジン登録・変更・解除→ https://www.bbook.jp
──────────────────────────────
発行元:藤井事務所 責任者:藤井孝一 (C) Copyright 1999-2008
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━